旭光通商株式会社 取締役
山西 幸男
光学技術製品の国際貿易におけるリーディングエキスパートとして、多くの日本企業の海外市場への進出をサポートしてきました。光安全性リスク評価の分野においても深い知識を有し、製品の国際基準適合性を確保するためのコンサルティングサービスを提供しています。
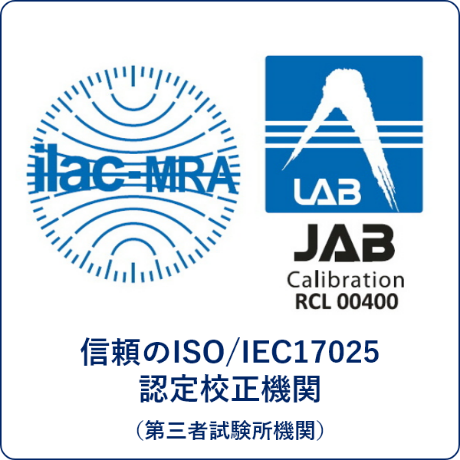
光は私たちの身の回りにある自然現象のひとつであり、その種類によって生体への影響も大きく異なります。本記事では、可視光・紫外線・赤外線という代表的な3種類の光に焦点を当て、それぞれの特徴、応用例、そして光安全性に関するポイントを比較形式で解説します。すでに「可視光の利用」や「人体系への影響」に関する情報は提供されていますが、本稿では光種別の比較と応用、リスク区分に着目し、より実践的な安全対策の視点を提供します。
この記事の監修

旭光通商株式会社 取締役
山西 幸男
光学技術製品の国際貿易におけるリーディングエキスパートとして、多くの日本企業の海外市場への進出をサポートしてきました。光安全性リスク評価の分野においても深い知識を有し、製品の国際基準適合性を確保するためのコンサルティングサービスを提供しています。
| 光の種類 | 波長範囲 | 特徴 |
|---|---|---|
| 紫外線 (UV) | 約100〜400nm | エネルギーが高く、殺菌・硬化・皮膚への影響が強い |
| 可視光 | 約380〜780nm | 人の目に見える光で、照明・視覚認識に利用される |
| 赤外線 (IR) | 約780nm〜1mm | 熱を持ち、リモコン・加熱・センサーに使われる |
| 光の種類 | 主な評価指標 | 代表的なリスク | 主な規格 |
|---|---|---|---|
| 紫外線 | 放射照度(W/m²) | 皮膚障害・眼障害 | IEC 62471, ISO 15858 |
| 可視光 | ブルーライト加重照度 | 視覚疲労・網膜障害 | IEC 62471 |
| 赤外線 | 熱量・曝露時間 | 熱傷・角膜損傷 | IEC 62471 |
光には種類があり、それぞれ波長やエネルギーが異なるため、安全性評価も一律ではありません。紫外線、可視光、赤外線はそれぞれ異なるリスクを持ち、用途に応じた対策が求められます。光安全性を確保するには、正しい知識と規格に基づいた管理が不可欠です。
最短7日間で校正完了光安全性の測定のご相談はこちら