旭光通商株式会社 取締役
山西 幸男
光学技術製品の国際貿易におけるリーディングエキスパートとして、多くの日本企業の海外市場への進出をサポートしてきました。光安全性リスク評価の分野においても深い知識を有し、製品の国際基準適合性を確保するためのコンサルティングサービスを提供しています。
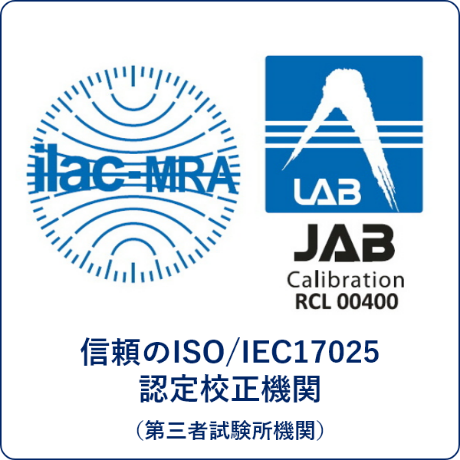
2024年6月1日に改定されたJIS T 5753「歯科用照明器」は、評価距離の明確化や照明域の定義更新、患者眼位置での評価追加など、設計・試験の前提を大きく見直しました。本稿では、IEC 62471(JIS C 7550)に基づく光生物学的安全性との接続も含め、開発・評価・申請・量産の各段階で必要となる実務手順を整理し、既存製品の移行チェックポイントまで体系的に解説します。
この記事の監修

旭光通商株式会社 取締役
山西 幸男
光学技術製品の国際貿易におけるリーディングエキスパートとして、多くの日本企業の海外市場への進出をサポートしてきました。光安全性リスク評価の分野においても深い知識を有し、製品の国際基準適合性を確保するためのコンサルティングサービスを提供しています。
目次
| 項目 | 旧JIS(2017) | 新JIS(2024) | 実務インパクト |
|---|---|---|---|
| 評価距離と照度条件 | 最高照度≧15,000 lx(距離の明確化が不十分) | 評価距離700 mmで中心照度≧15,000 lx | 測定幾何の固定化。治具・手順を700 mm基準へ更新。 |
| 照明域の定義 | 最高照度点中心の実用域 | 等照度線で囲まれるA/B領域 | 均斉度・配光評価が客観化。報告書様式の見直しが必要。 |
| 患者眼位置評価 | ― | C領域(患者眼位置)での照度評価を追加 | 眩しさ・快適性対策の設計要件が強化。遮光・配光制御が重要。 |
JIS T 5753:2024は「評価距離の固定(700 mm)」「等照度線による照明域」「患者眼位置の追加評価」により、“見やすさ”と“安全”を両立させる設計指針を明確化しました。開発側は光学設計・測定幾何・文書化の三位一体で更新し、IEC 62471評価を流れに組み込むことで、国内外での適合性と臨床受容性を確実に担保できます。
光生物学的安全性評価、等照度マッピング、分光測定/校正のご相談を承ります。
電話:03-6371-6908(平日 9:00–17:00)
サービス:光生物学的安全性評価、光源・測定機器の校正(ISO/IEC 17025に準拠)
カテゴリー:特定用途における光安全性/医療機器安全基準
著者・監修:旭光通商 光学試験校正室/技術部門
初回公開日:2025-11-05(JST)/最終更新:2025-11-05(JST)
最短7日間で校正完了光安全性の測定のご相談はこちら