旭光通商株式会社 取締役
山西 幸男
光学技術製品の国際貿易におけるリーディングエキスパートとして、多くの日本企業の海外市場への進出をサポートしてきました。光安全性リスク評価の分野においても深い知識を有し、製品の国際基準適合性を確保するためのコンサルティングサービスを提供しています。
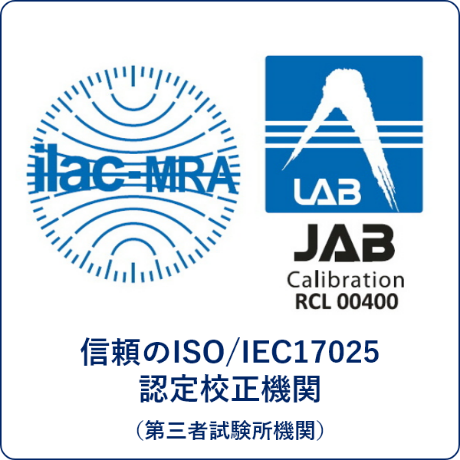
光安全性に関連する文献や規格を正確に理解するためには、基本となる用語の理解が欠かせません。本記事では、光物理、光測定、安全評価に関する専門用語を厳選し、技術者や管理者が現場で活用できるレベルで体系的に解説します。これらの用語は、IEC 62471をはじめとする国際規格や光測定機器の使用において基本となる概念です。
この記事の監修

旭光通商株式会社 取締役
山西 幸男
光学技術製品の国際貿易におけるリーディングエキスパートとして、多くの日本企業の海外市場への進出をサポートしてきました。光安全性リスク評価の分野においても深い知識を有し、製品の国際基準適合性を確保するためのコンサルティングサービスを提供しています。
光の一周期あたりの長さ。単位はナノメートル(nm)。波長により紫外線、可視光、赤外線に分類され、光のエネルギーや生体影響に関与する重要なパラメータ。
単位時間あたりの振動数。波長と反比例の関係を持ち、エネルギーとの換算に用いられる(E = hν)。単位はヘルツ(Hz)。
光を構成するエネルギー粒子で、量子単位。光源の放射特性を理解する際の基本単位であり、エネルギー評価や量子効率計算に不可欠。
照射面1平方メートルあたりの光エネルギー量(単位:W/m²)。紫外線ランプやLEDなどの安全評価において中心的な測定項目。
光源や物体表面から発せられる光の見た目の明るさ(cd/m²)。視認性評価やディスプレイ製品設計の評価基準となる。
光源が発する光の波長別強度分布。LED、レーザー、蛍光灯などの分類と安全性評価における基本情報。
波長400〜500nmの青色光に起因する網膜損傷リスクの指標。視認性が高い一方で、曝露時間・強度により生体影響が生じるため、特にディスプレイ・照明機器の設計で重視される。
IEC 62471において定義された光源の危険度分類。RG0(無害)〜RG3(高リスク)までの4段階で構成され、製品仕様・注意表示義務に影響を及ぼす。
光源に曝露しても安全とされる最大エネルギー量。測定単位や評価時間、波長帯ごとに定義されており、設計・試験基準の指針となる。
光安全性に関する用語は、設計、規格適合、教育・啓発活動すべての基礎となります。今回取り上げた用語を出発点に、リスク評価や対策立案における理解を一層深めていきましょう。光学的安全管理において、精確な用語知識は信頼性と法的適合性の土台です。
最短7日間で校正完了光安全性の測定のご相談はこちら