旭光通商株式会社 取締役
山西 幸男
光学技術製品の国際貿易におけるリーディングエキスパートとして、多くの日本企業の海外市場への進出をサポートしてきました。光安全性リスク評価の分野においても深い知識を有し、製品の国際基準適合性を確保するためのコンサルティングサービスを提供しています。
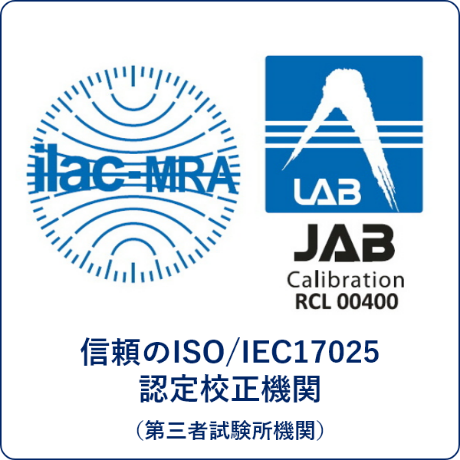
私たちは通常、光を「見る」ための手段として認識しています。しかし、光は視覚以外にも様々な生体反応を引き起こす可能性があり、特に人工光環境が高度化した現代では、光曝露の影響が無視できないものとなっています。本記事では、「視覚に現れない光の影響」に着目し、睡眠障害、ホルモン分泌、皮膚免疫など多様な観点から光安全性の重要性を再考します。
この記事の監修

旭光通商株式会社 取締役
山西 幸男
光学技術製品の国際貿易におけるリーディングエキスパートとして、多くの日本企業の海外市場への進出をサポートしてきました。光安全性リスク評価の分野においても深い知識を有し、製品の国際基準適合性を確保するためのコンサルティングサービスを提供しています。
人間の体内時計(サーカディアンリズム)は、主に青色光(波長450〜480nm)によって調整されています。夜間にスマートフォンやLED照明から発せられる青色光に曝露されることで、メラトニンの分泌が抑制され、入眠困難や睡眠の質の低下を引き起こすことが知られています。
光曝露は副腎皮質ホルモンやセロトニンの分泌にも影響を与えることが報告されています。朝の光は覚醒と気分の安定に寄与しますが、日中・夜間の過剰な照度はストレスホルモンの過剰分泌を促し、自律神経のバランスを乱す原因となります。
紫外線による皮膚がんのリスクは広く知られていますが、赤外線や強い可視光の長時間曝露も皮膚の炎症や免疫低下を引き起こす可能性があります。特に医療用光源(オペ室、光線療法)では慎重な設計と管理が必要です。
光安全性の議論は、単に「まぶしさ」や「視力への影響」だけでは不十分です。照明のスペクトル分布や照射時間、位置、空間デザインは、長期的な健康影響に直結します。光源選定時には、IEC 62471に加えて、人間工学や睡眠科学の知見も取り入れる必要があります。
乳幼児、高齢者、睡眠障害を持つ人々は、光の影響を受けやすいとされています。特に保育施設、病院、老健施設においては、光曝露の質と量を適切に制御することが重要です。
光は単なる照明ではなく、生理機能や行動に影響を及ぼす環境因子です。従来の視覚中心の安全性評価に加えて、非視覚的影響に配慮した光環境の整備が求められています。照明設計、光源開発、環境マネジメントに関わるすべての人が、光安全性の本質を理解し、総合的なリスク低減を図るべき時代に来ているのです。
最短7日間で校正完了光安全性の測定のご相談はこちら