旭光通商株式会社 取締役
山西 幸男
光学技術製品の国際貿易におけるリーディングエキスパートとして、多くの日本企業の海外市場への進出をサポートしてきました。光安全性リスク評価の分野においても深い知識を有し、製品の国際基準適合性を確保するためのコンサルティングサービスを提供しています。
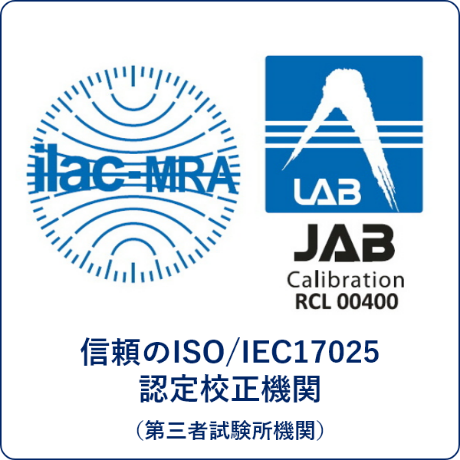
JIS C 6802:2025(レーザ製品の安全―クラス分け及び要求事項)は、IEC 60825-1:2014に整合しつつ、 参考附属書(JA/JC/JD)でIEC/TR 60825-14:2022(ユーザーズガイド)の考え方を反映しました。 公示日は2025年8月20日。クラス分けの枠組み(1/1M/2/2M/3R/3B/4)と適用範囲(180 nm~1 mm)は継続ですが、 現場運用(教育、LSO、区域管理、記録)の解像度が上がっています。本稿では「改正の要点」「手順」「チェックリスト」「FAQ」を体系的に整理します。
この記事の監修

旭光通商株式会社 取締役
山西 幸男
光学技術製品の国際貿易におけるリーディングエキスパートとして、多くの日本企業の海外市場への進出をサポートしてきました。光安全性リスク評価の分野においても深い知識を有し、製品の国際基準適合性を確保するためのコンサルティングサービスを提供しています。
目次
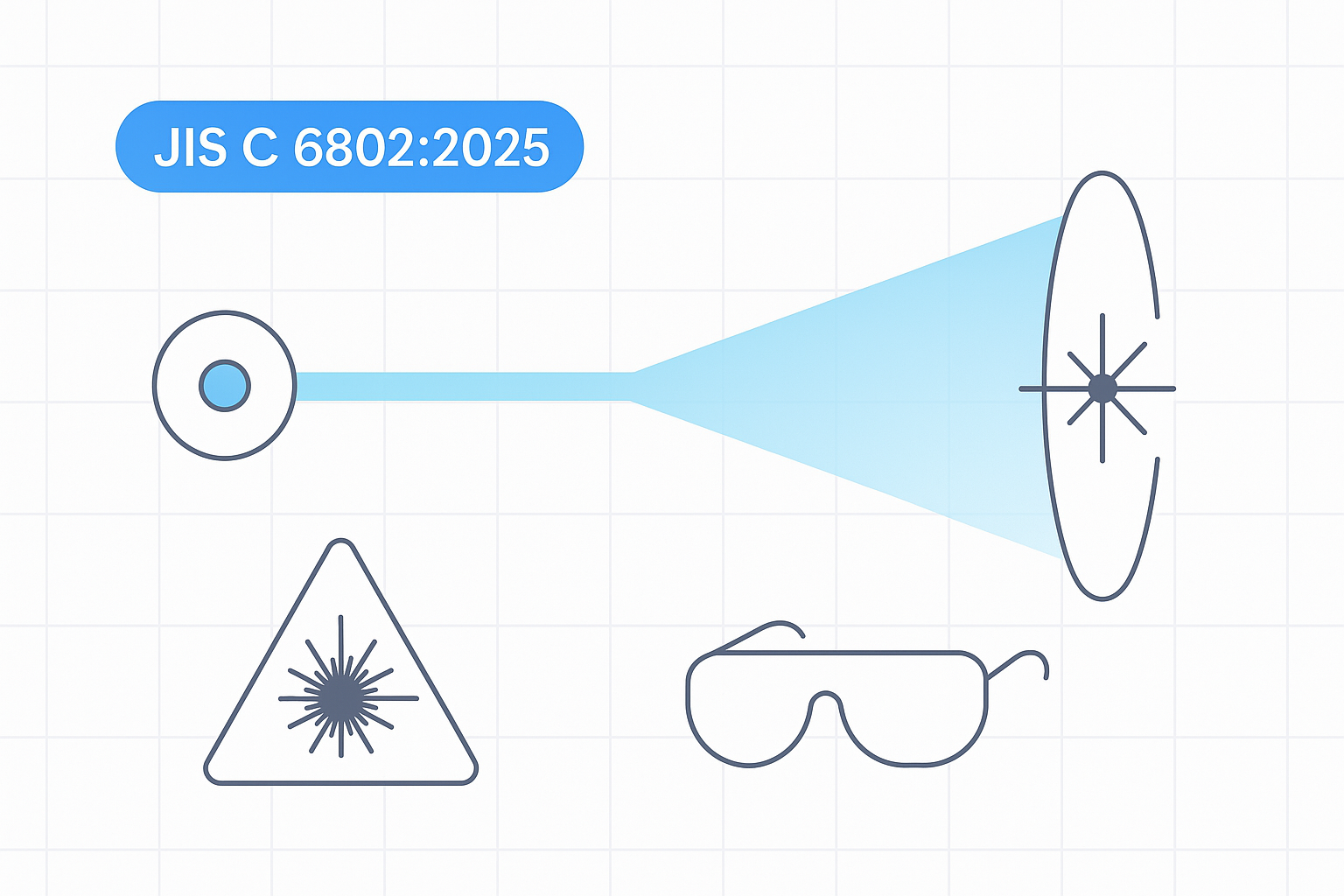
※最終判断は必ず規格本文(最新の改訂票を含む)に従ってください。
LSOの任命、権限(停止・教育承認・区域許認可・事故審査)を明確化。役割と権限は文書で付与し、年次見直しを推奨。
作業手順・ビーム経路・迷光・反射を含めたリスク評価を更新。インシデントの受付・是正・再発防止プロセスと医監の考え方を整理。
常設区域と一時区域の使い分け、入退管理、標識、インタロック点検、PPE選定の参考を体系化。
波長域・暴露時間・観察条件(裸眼/光学器具/拡張光源)ごとの適用表・式、補正係数(例:Ca, Ce, Ct, C6)を明示し、根拠の再現可能性を重視。
クラス別の代表リスクと必須コントロール、取扱説明書(IFU)・警告表示の要点を整理します。
| クラス | 主要コントロール | 補足 |
|---|---|---|
| 1 / 1M / 2 / 2M | 標識・教育、ビーム経路の最短化、基本遮光。1M/2Mは光学器具視認リスクに留意。 | 一般占有空間での誤用・光学器具視認を想定して確認。 |
| 3R / 3B | LSO必須、区域化、入退管理、PPE、ビームストップ、調整時手順の分離。 | 来訪者・保守作業の手順書を別管理。 |
| 4 | 遮蔽・連動、安全監視、火災対策、厳格な訓練・監査。 | 迷光・反射・発火を含む総合管理が前提。 |
| 項目 | 改定前(〜2025改正前) | 今回改定後(2025版) |
|---|---|---|
| 規格本体の枠組み | 180 nm〜1 mmのレーザ製品の安全要求とクラス分け。IEC 60825-1:2014ベース。 | 枠組み継続。クラス体系・基本概念に大変更なし。 |
| 附属書(使用者への指針) | 旧来のガイドをJIS独自附属書に維持。 | IEC/TR 60825-14:2022の考え方を反映し、教育・LSO・区域・保守・MPE記録など実務を整理。 |
| ユーザー向け情報提供 | IFU中心(一般的対策が主)。 | 教育計画・区域運用・緊急時対応・測定/記録の粒度を向上。 |
| MPE運用 | 定義・評価は従来通り。テンプレは各社設計。 | 前提・式・係数を明示して再現性ある記録を推奨。 |
| 実装の着眼点 | クラス3R以上で区域化・PPE・手順分離。 | 保守・来訪者・一時区域など、事故起点になりやすい場面の整理を強化。 |
JIS C 6802および関連ガイダンスの該当表・式を参照して記入してください(SI単位系)。
例:λ=532 nm, CW, t=0.25 s, 小光源の仮定 → 可視域・網膜曝露の区分を参照し、必要な補正(例: C_a, C_t 等)を適用してMPEを決定。測定した放射輝度/照度と比較して適合性を判断。
波長・出力(CW/パルス)・ビーム径/発散・観察条件を特定し、該当する測定条件と限度(MPE)からクラスを導出します。IFU・ラベル要件も同時に見直してください。
部門横断で停止権限・教育承認・区域許認可・事故審査の権限を持つ責任者を任命。年次で教育と権限を更新します。
波長域と暴露時間に対応する表・式を引用し、前提・補正係数・評価量・測定配置を可追跡に残します。
据付・保守・調整等では一時区域化を原則。インタロックは点検周期・試験記録・是正のプロセスを文書化します。
※リンク先の原文・最新改訂票を必ず確認してください。
JIS C 6802:2025は、クラス分け等の枠組みは維持しつつ、使用者側の運用指針(教育・LSO・区域・記録)を最新化しました。 製造者はIFUとラベルの整合・改訂、ユーザーはLSO任命・区域化・MPE記録の体系化を優先してください。 保守・一時区域・来訪者対応は事故が起きやすい領域です。チェックリストとワークシートで可視化し、年次監査に組み込むことが、 最短距離の適合と安全文化の醸成につながります。
最短7日間で校正完了光安全性の測定のご相談はこちら