旭光通商株式会社 取締役
山西 幸男
光学技術製品の国際貿易におけるリーディングエキスパートとして、多くの日本企業の海外市場への進出をサポートしてきました。光安全性リスク評価の分野においても深い知識を有し、製品の国際基準適合性を確保するためのコンサルティングサービスを提供しています。
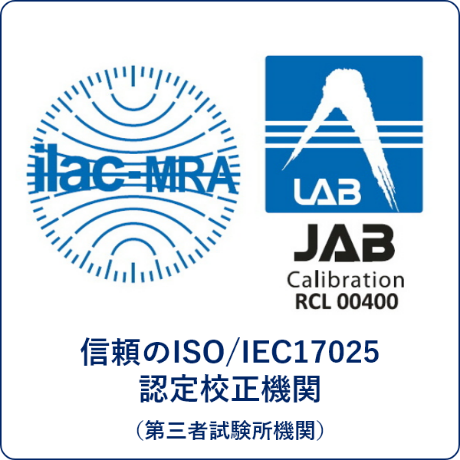
LEDやUV光源の用途拡大に伴い、製品の光生物学的安全性(眼・皮膚への影響)をIEC 62471/JIS C 7550で適正に評価する重要性が高まっています。本稿では、JIS C 7550:2011の追補1(2014)による改正の位置づけと、2019年の制度改正に伴う名称読み替え、さらにIEC 62471-5(プロジェクタ)やIEC 62471-6(UVランプ製品)といった最新動向を踏まえ、実務者が迷いやすい「測定条件・判定ロジック・表示義務」の要点をチェックリストとともに体系的に解説します。評価対象のハザード、測定パラメータ、境界規格(レーザ JIS C 6802、IEC/TR 62778)との関係まで一通り押さえれば、設計段階でRG0/RG1を狙ったリスク低減が可能になります。
この記事の監修

旭光通商株式会社 取締役
山西 幸男
光学技術製品の国際貿易におけるリーディングエキスパートとして、多くの日本企業の海外市場への進出をサポートしてきました。光安全性リスク評価の分野においても深い知識を有し、製品の国際基準適合性を確保するためのコンサルティングサービスを提供しています。
目次
| ハザード | 記号 | 主な波長域 | 主対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 作用紫外線(アクチニックUV) | ES | 200–400 nm | 眼・皮膚 | 有効重みS(λ)で実効化(時間依存) |
| 近紫外(眼) | EUVA | 315–400 nm | 眼 | 角膜/水晶体リスク(時間依存) |
| 青色光網膜 | EB / LB | 300–700 nm(主に400–500 nm) | 眼(網膜) | 小形光源は輝度(LB)、大形は照度(EB)で評価 |
| 網膜熱 | LR | 380–1400 nm | 眼(網膜) | 短時間パルスに注意 |
| 皮膚・眼の熱(IR) | EIR / LIR | 780–3000 nm | 皮膚・角膜 | 近赤外の熱負荷 |
※小形/大形光源の切替は見かけ視角(α)で判断。αが所定閾値以下なら小形光源→輝度評価(L●)、超える場合は大形光源→照度評価(E●)が基本です。
以下の動画(株式会社ラッシュカラーズ様 × 光学試験校正室)では、当社の光学試験・校正に関する取り組みと、お客様視点での活用イメージを紹介しています。本記事の第3章(測定・判定)および第6章(実務チェックリスト)と併せてご覧いただくと、JIS C 7550(IEC 62471)評価の全体像が短時間で把握できます。
JIS C 7550は、IEC 62471の枠組みを国内展開した横断規格であり、2014追補による用語整備と2019年の名称読み替え以降、技術要求は堅調に運用されています。近年はIEC 62471-5/-6が個別製品領域(プロジェクタ、UV製品)で要求を具体化しており、国内JISの動向に先駆けた設計・評価・ラベリングの先取りが実務的なリスク低減につながります。評価は最悪条件で幾何・時間・分光を正しく定義し、小形/大形の切替、パルスの扱い、ユーザー情報の整備まで含めて一貫性を確保することが肝要です。
最短7日間で校正完了光安全性の測定のご相談はこちら