旭光通商株式会社 取締役
山西 幸男
光学技術製品の国際貿易におけるリーディングエキスパートとして、多くの日本企業の海外市場への進出をサポートしてきました。光安全性リスク評価の分野においても深い知識を有し、製品の国際基準適合性を確保するためのコンサルティングサービスを提供しています。
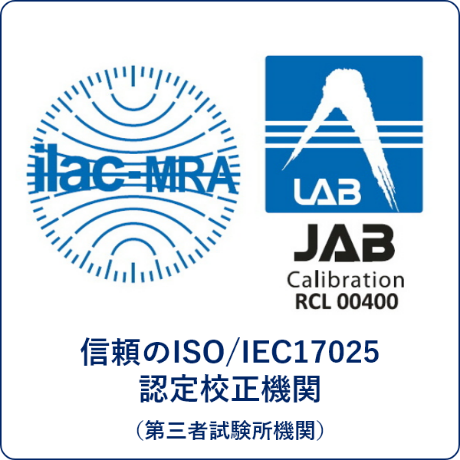
JISの5年見直しは、公示後おおむね5年で適正性を再点検し、確認・改正・廃止を決める制度です。2025年度は2021年度公示JISが中心で、JSA本調査の回答期限は2025/9/30、一般意見は2025/9/16まで。本記事は制度の流れと関係者の役割を簡潔に整理し、光安全性―レーザ安全(JIS C 6802/IEC 60825-1)と光生物学的安全(JIS C 7550/IEC 62471-7)―の要点を、測定幾何・分光加重・MPE/ELV・クラス/RG判定・ラベル/IFUの実務観点で解説します。2025年8月改正のJIS C 6802とIEC 62471-7解釈票への対応手順も提示し、短時間で抜け漏れなく準備できるチェックリストを付けました。
この記事の監修

旭光通商株式会社 取締役
山西 幸男
光学技術製品の国際貿易におけるリーディングエキスパートとして、多くの日本企業の海外市場への進出をサポートしてきました。光安全性リスク評価の分野においても深い知識を有し、製品の国際基準適合性を確保するためのコンサルティングサービスを提供しています。
| 区分 | 期日 | 備考 |
|---|---|---|
| 事前調査 | 2025-05-30 | 調査対象JISリスト確定と配布(JSA) |
| 本調査 | 2025-09-30 | 原案作成団体からJSAへ回答(JSA) |
| 一般意見 | 2025-09-16 | 経産省JISC窓口へ提出(JISC) |
※期限は公式告知の記載に従う。
| 分類軸 | 光源種別 | 規格 | 主なアウトカム |
|---|---|---|---|
| レーザのクラス | コヒーレント(レーザ) | JIS C 6802 / IEC 60825-1 | Class判定、MPE/NOHD、ラベル・IFU |
| リスクグループ | 非コヒーレント(LED等) | JIS C 7550 / IEC 62471 | RG判定、ELV(曝露限界)、表示・IFU |
JISの5年見直しは、産業標準化法に基づく計画的なメカニズムであり、2025年度は2021年度公示のJISが中心となる。光安全では、JIS C 6802の2025年改正とIEC 62471-7の補足文書が重要で、測定・判定・表示の見直しが求められる。調査票では、上位規格の更新状況と自社製品・サービスの曝露管理の適合性を、測定データとIFU草案を添えて具体的に示すことが、確認・改正判断を適正化する鍵である。
最短7日間で校正完了光安全性の測定のご相談はこちら