旭光通商株式会社 取締役
山西 幸男
光学技術製品の国際貿易におけるリーディングエキスパートとして、多くの日本企業の海外市場への進出をサポートしてきました。光安全性リスク評価の分野においても深い知識を有し、製品の国際基準適合性を確保するためのコンサルティングサービスを提供しています。
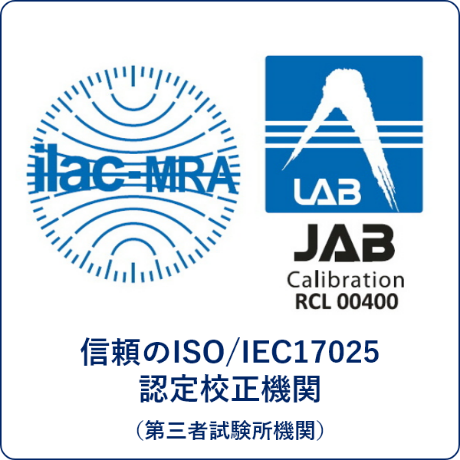
2024年6月1日施行のJIS T 5753「歯科用照明器」改定では、歯科診療における照明品質を飛躍的に高めるため、光源のスペクトル分布測定と最新の色再現評価手法が新たに導入されました。これにより、従来の照度中心評価だけでは見えにくかった微細な色差再現性や、長時間使用時の光質変化までを定量的に把握可能に。改定ポイントを正しく理解し、試験プロトコルの見直しや社内体制整備を行うことが、診療精度向上と規格適合の両立に不可欠です。本記事では、光学測定方法と色評価方法の変更点をわかりやすく整理し、歯科用照明器メーカー・設計者が今すぐ取り組むべき対応ステップとメリット・デメリットを解説します。
この記事の監修

旭光通商株式会社 取締役
山西 幸男
光学技術製品の国際貿易におけるリーディングエキスパートとして、多くの日本企業の海外市場への進出をサポートしてきました。光安全性リスク評価の分野においても深い知識を有し、製品の国際基準適合性を確保するためのコンサルティングサービスを提供しています。
2024年6月1日施行のJIS T 5753「歯科用照明器」の改定では、歯科診療における光源の安全性・再現性をさらに高めるため、光学的測定方法と色の評価方法が見直されました。従来の照度中心の評価から、スペクトル分布や色再現性を詳細に規定し、診療精度への貢献を強化するための改定です。
JIS T 5753改定により、歯科用照明器の光質と色再現性評価は従来以上に厳密化されました。スペクトル分布と最新の色再現指標TM-30を導入することで、臨床現場での色判別精度が向上します。一方で、測定機器の導入コストや社内教育が必要になるため、自社体制を早めに整備し、改定対応スケジュールを策定しましょう。
最短7日間で校正完了光安全性の測定のご相談はこちら